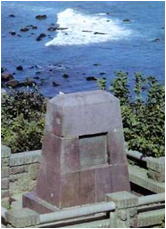| 石 川 節 子 (9) | |||||||
啄木は堅苦しい学校よりも新聞社はある程度の自由もあり、何よりも文学の記事を書けるのが性分に合っていたと思う。彼は入社早々「月曜文壇」とか「日々歌壇」などを設けて評論「辻講釈」なども書いた。それ以後生涯にかけて新聞社は数度変わったが、新聞社に最後まで勤めた。しかし彼は、一週間ほど勤務したに過ぎず。またも彼の身に大災害がふりかかってきたのである。八月の二十五日夜、東川町の石鹸工場から発した火災は折からの強風にあおられて、たちまち全市街の三分の二を焼き尽くし暁にいたってやっと鎮火した。焼失家屋一万二千三百九十戸、死者八名という大惨事となったのである。函館という街は三方が海に囲まれている地形のため、強風のあるときに火災がおきるとたちまち大火になる危険をはらんでいるのであって、明治時代を調べてみても、百戸以上焼失したのが十九回あり、その内、千戸以上の焼失は六回を数えるが、今回の四十年の大火は最大のものであった。啄木の住居は幸い被害を免れたが、勤務先である「弥生尋常小学校」や「函館日日新聞社」などは焼失した。
彼はことごとく函館での生活基盤を失ったのである。こうした大火災などに遭遇した経験は全くなかった啄木が、どのような感想もったかということは彼の日記に詳しい。「市中は惨状を極めたり。町々に猶処々火の残れるを見、黄煙全市の天を覆ふて天日を仰ぐ能はず。」と、また「狂へる雲の上には、狂へる神が狂へる下界の物音に浮き立ちて狂へる舞踏をやなしにけん。大火の夜の光景は余りにわが頭に明らかにして、予は遂に何の語を以って之を記すべきかを知らず。火は大洪水の如く街を流れ、火の粉は夕立の雨の如く降れりき、全市は火なりき。」私は函館最大の昭和九年の大火を経験しているので、啄木の記述はよく理解できる。私の体験は明治時代とは違い、人口も二十万を越えていたし、市街も倍には大きくなっていた、その三分の二を焼失するという大災害であった。 しかし啄木というのは、恐怖というよりも面白がっているという常人とは違った感情を持っているようである。次の記述を日記から引いてみよう。「高きよりこれを見たる時、予は手を打ちて快哉を叫べりき。予の見たるは幾万人の家を焼く残忍の火にあらずして、悲壮極まる革命の旗を翻し、長さ一里の火の壁の上より函館を覆へる真っ黒の手なりき。」「かの夜、予は実に愉快なりき、愉快とふも言葉当らず、予は凡てを忘れてかの偉大なる火の前に叩頭せむとしたり、一家の危安豪も予が心にあらざりき、幾万円を投じたる大高楼の見る間に倒るるを見て、予は寸厘も愛惜の情を起こすなくして心の声のあらむ限りに快哉を絶呼したりき。」普通の人間であれば、大災害に直面してこうした感想を抱く者はまずないだろう。「一家の危安豪も予が心にあらざりき」家族に気を使うこともなければ、勤務先を全て失う事態に至りながら、彼の感想は異常だというほかはない。 だが札幌から帰ってきた同人向井と相談し、もし札幌に就職口があれば札幌に移転しようと思い、彼に履歴書を預けた。向井からは十日ほどして「北門新報」に校正係の職があるとしらせてきた。啄木は迷うことなく札幌移住を決めた。せっかく函館に来てやっと四散した家族を集め、これから楽しい生活が待っていると思った矢先に、またまた流浪の生活に落とされるなど考えてもいなかったと思うが、節子などはたったの二ヶ月啄木と暮らしただけであった。不運な一家というほかはない。 明治四十年九月十三日啄木が発つ日、駅には節子親子と友人五人が送ってくれた。翌日早朝四時に小樽へ着き、姉夫婦の山本家に立ち寄って、妻子が後ほどお世話になることを告げ、再び十一時半の列車で札幌に向かった。駅には同人向井と松岡が迎えに来ていた。向井の厚意でその下宿を当分の宿舎にしたが、啄木は札幌の印象を次のように記している。「札幌は大いなる田舎なり、木立の都なり、秋風の都なり、しめやかなる恋の多くありそうな都なり。詩人の住べき地なり。」と延べて港町とちがう風景に心引かれたようであるが九月十六日啄木は「北門新報社」に初出勤した。午後二時から八時までの勤務で月給は十五円であった。
啄木は例によって、一校正係の身でありながら、入社草々「北門歌壇」を起こし、また「秋風記」といった感想文を書いたりしている。「北門新報」は発行部数六千ほどの新聞であるから、勝手なことができるのであろう。それから数日後の夜、露堂が訪ねてきての話に、今度小樽に新しい新聞が出来るが、入らないかという相談であった。野口雨情も行くという。啄木にしてみれば、小樽なら姉夫婦の山本家に節子親子も同居していることだし、新聞の創刊というのも魅力的だったのだろう。啄木は全て好都合なので、即座に小樽への移転を決断した。啄木は野口雨情という詩人の名前は、知ってはいたが、本人に面識がなかったので、これから共に「小樽日報」で仕事をする相手として少々気になっていたのだと思う。その点、露堂に雨情がどのような人物なのかを聞いてみた。露堂は「二回ほど会ったが、温和で丁寧な人だ」と話した。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||
| 井上信興先生の 啄木研究 塚本 宏 |
著書 (表示後「文芸評論」 をクリックください) |
掲載にあたって |