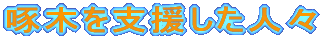
| 5.「東京朝日新聞社」の人々(2) | |||||||||||||
編集の上田芳一郎氏によると、「佐藤君の性質は一体に真面目嫌いの方であった。清獨あわせ呑むという度量はあったけれども几帳面なものはあまり喜ばなかった。彼は如何なる場合といえども、威容を正すといふよりも先ず笑顔してこれを迎えるという風であった」という。
啄木はこうした上司がいたことによって、以後の人生を送ることが出来たとも言える。と言うのも、例によって少し勤務に慣れると自己都合で仕事を休むのである。まだ入社してひと月半にしかならない四月十七日「今日こそ必ず書こうと思って社を休んだ。」つまり小説を書くために社を休むのである。また翌日の日記に「十一時までも床の中でモゾモゾしていた。社に行こうか、行くまいかという、たった一つの問題をもてあました。」また少しすると、「そうだあと一週間くらい社を休むことにして大いに書こう。」「社を休んでいる苦痛も慣れてしまってさほどでない。」 啄木という人物は勤務者としての資質をまったく持っていないということがこうした記述から断定できる。 さて上京してきた家族であるが、もともと母かつは、啄木の結婚相手としての節子に不満を持っていたから、同居生活がうまくいくはずはなかった。この二人の感情は日増しに先鋭となっていった。そうした頃、節子の妹ふき子が宮崎郁雨氏に嫁ぐことが決まり、節子としては、姉として準備を手伝いたい、とかまた話しておきたいこともあっただろう。それに函館に去ってしまえば、会う機会も簡単には出来ないだろう。私が去れば、家事のすべてが母かつの仕事になり、少しは有難味がわかるだろう。といった判断から、盛岡へ行かせてくれと申し出たが、啄木は許さなかった。 十月二日朝、節子は京子を連れて家出したのである。後には置手紙がのこされていた。「私ゆえに親孝行のあなたを御母さんにそむかすのは悲しい。私は私の愛を犠牲にして身を退くから、どうか御母さんへの孝養を全うして下さい。」という。これまで啄木としても、不仲な二人については、気にかけてはいたものの、まさか妻が家出をするなどとは全く考えてはいなかっただろう。それだけに彼のうろたえ様は尋常ではなかった。
こうした時に頼れるのが金田一氏しかいないと思い、彼の下宿へ跳んで行った。とにかく節子が帰って来るように手紙を出してほしいと頼んだ。「私が可哀想だ、意気地なく泣いていると書いてもいいし、私を馬鹿だと書いてもいい、」とすべてを彼に一任した。気の強い啄木もこの件に関しては、まるで無条件降伏といった有様なのである。金田一氏は即座に啄木の求めに応じ「私は長い長い手紙を、仕舞には自分の妻でも逃げたやうに、ぼろぼろ涙を落としながら書いた。これなら帰らずにはおれまいと思うような名文を書いたつもりだった。」 啄木はそれでも不安だったのだろう、盛岡高等小学校時代の恩師新渡戸仙岳にも手紙を送り、くどくどと家出の経緯を述べた後に、「一日も早く戻ってくるや御命じ被下度伏して願い上げ奉り候。」とある。 こうした手紙をもらった節子は、啄木がこれほどショックを受けるとは思っていなかっただろう。節子が離婚を覚悟して家出したと私には思えない。困るのは母親で、家事を背負えるはずはないから、啄木とて早く帰ることを願うに違いない。節子にしても、結婚する際、父親の絶対反対を押し切って自己の想いをとげたほどの彼女であるから、その意思は強いものを持っていた。それが駄目でしたと実家に帰ることは出来ないだろう。節子は二十四日ぶりに東京へ帰ってきた。 啄木は「節子が家出したのはおっ母さんのせいだ」と言って責めたので反省したのであろう。節子が妹ふき子への手紙に、「おっ母さんはもう閉口して弱り切っていますから何も小言など言いません。」と書き送っている。流石の老母も嫁の家出には勝てなかったようである。 話をまた新聞社に戻すと、勤務状態の甚だ悪い啄木だったがその才能だけは認められているようで、主筆の池辺三山氏から、「二葉亭四迷全集」の校正を依頼されて、その作業に従事した。宮崎郁雨氏への手紙に、「お陰で、二葉亭といふ非凡なる凡人をよほど了解することが出来た。」というから、彼にとってそう悪い仕事ではなかった。また社会部長の渋川玄耳氏は、新聞に出した啄木の歌をみて、「大変褒めてくれた。」そればかりではない。
「東京朝日新聞」は「歌壇」の選者に啄木を抜擢したのである。東京の一流紙ともなれば、普通有名な歌人を選者に迎えるものだが、渋川部長の決断で決定した。明治四十三年九月十日から翌年二月二十八日まで八十二回に及び、投稿者数百八十三名、総歌数五百六十八首、であった。これによって啄木の名が一応全国に知られたと思う。 そして氏は、「出来るだけの便宜を与えるから、自己発展の手段を考えてきてくれ。」と言った。啄木は迷う事なく歌集の出版を計画したのである。彼は自作のノートから二百五十五首を選出して題名を「仕事の後」とした。そして「東雲堂」に二十円で買い取ってもらったが、凝り性の彼は出版がきまってから歌数、表題、歌の形式など大幅に変更した。表題を「一握の砂」として大森浜での感慨十首を巻頭に据え、全歌を三行書きにしている。この変更は読者にこれまでにない新鮮さを与えた。 翌明治四十四年一月、啄木の体に変調が現れた。日記に、「腹がまた大きくなった様で、座っていても多少苦しい。」そして二月一日東大病院を受診した。医者は一目見て「これは大変だ、早く入院せよ」という。「慢性腹膜炎」であった。二月四日。に入院した。
したがって以後社は欠勤した。一ヶ月もすると、入院に厭きて、退院したくなったようだが、その頃から高熱が出るようになった。肋膜炎を併発したのである。しかし三月十五日啄木の希望を入れ、無理を承知で病院は退院を許可した。だが退院以後毎日のように八度前後の発熱が続いた。啄木の命は間違いなく終局にむかっているのだ。 一方「朝日新聞社」としても、勝手に休むことの多い啄木について人事の関係者は会社にとって好ましい勤務者とは到底思われていなかっただろう。つまり退職していないからには、まったく仕事をしていない者にも、月給を出し続けているのである。 したがって、佐藤編集長に「石川をどうする」と、処分を含めた問いに、佐藤氏は「まあ放っといてくれたまえ」と答えている。この一言で啄木の首が死ぬまで繋がったのである。また、杉村学芸部長からは、社員に義援金をつのり十七名から三十四円四十銭を集めて、佐藤編集長がわざわざ届けてくれた。佐藤氏は入社から、死に至るまで在社させ、渋川部長は歌壇の選者を命じ、歌集「一握の砂」出叛の手掛かりを与えた。こうした点を見ても、啄木というのは、周囲に必ず善意の人がいたのである。 |
|||||||||||||
| もくじに戻る | |||||||||||||



