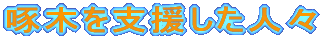
| 5.「東京朝日新聞社」の人々(1) | |||||||
| 啄木は釧路を脱出し再びなつかしい函館に帰ってきた。久しぶりに同人たちと酒をくみかわして話しもはずんだ。啄木にしてみれば、数年は函館で暮らし、時が来たら上京して文学で独立したいと考えていた。上京の話が出ると、宮崎氏は、その気があるのなら一日も早いほうがいい、と言ってくれた。その間責任をもって妻子は預かる。という願ったりかなったりの話である。 啄木は翌日早速小樽に残している妻子の許に行った。小樽も一年ぶりである。「小樽日報」も近々廃刊することになったという。啄木が自ら退社しなかったとしても、結局は一年後に退社する運命になっていたのだ。小樽には六日滞在し家族四人で小樽を去った。宮崎氏の配慮で栄町の鈴木氏の二階に居を定める。食料品や寝具などすべて宮崎氏が用意してくれた。これで啄木も安心して上京できることになった。啄木が函館を去ったのは、明治四十一年四月二十三日のことであった。午後四時宮崎、吉野の二君に送られて海路三河丸で函館を後にした。
上京の節は与謝野氏宅に来るようにという手紙をもらっていたので氏の宅で一週間ほど世話になったが落ち着かぬ状態で何時までもここにもおれず、盛岡中学の先輩で親友の金田一京助氏の下宿、菊坂町の赤心館を訪問することにした。下宿について氏に相談すると、ついつい話がはずんで、その夜は氏の部屋に泊まった。翌日この下宿の一部屋を提供され、金田一氏が机と椅子まで用意してくれた。 これで落ち着いて小説に没頭できる。短編よりは長編を書きたいと考えてはいるが、五月八日の日記に「短編より長編を書きたいが、長編は書ききらぬ内に飢えるという心配がある。早く何とか下宿料を払える道を得たいと考える。」と言い、小説が売れれば金になると思っているのだろうが、彼が考えているほどこの道の厳しさがまだわかっていない。それでも三本ほど脱稿し、金田一氏に読んでもらった。氏は「中央公論社」に持って行ってくれた。六月三日の日記に、皮肉を込めて「病院の窓と母、戻ってきた無事に」と書いている。その後森鴎外氏の留守に自宅を訪問し、小説二作を置いて帰った。何せ収入がないのだから、用紙が尽きれば書くことが出来ないのである。 与謝野氏が啄木に任せた投稿歌二通の為替が来ていて、すぐ金に変えて原稿用紙を買うことが出来た。鴎外宅に置いてきた小説、二作について、森氏から「春陽堂」が買い取ってくれるという連絡を受けた。しかし報酬は掲載の後、ということですぐ金になる話ではなかった。だがこの原稿は後に金にはなったが掲載されることはなかった。啄木が度々催促するのと、森鴎外氏の顔を一応立てる意味もあったからであろう。 そうしてる間に啄木にも幸運が舞い込んだ。小説「鳥影」が「東京毎日新聞」に連載されることになったのである。これは「新誌社」の友人栗原古城氏の斡旋によるものである。この執筆料は一回一円であったから月三十円という結構な金額ではあるが、これは定収入ではない。忽ち支払いに消えてゆく運命にある。啄木は上京以来先輩の金田一氏に多額の損害をかけてきた 自分も何かで定収入の道を考えなければ、生活も成り立たないと思い。思案した結果「朝日新聞社」の編集長が同郷の佐藤北江氏であることを知っていたのであろう。地方新聞とは違い、相手は東京の一流新聞であるから、流石の啄木も、駄目でもともとと言ったつもりで履歴書と雑誌「スバル」を送ってみたのである。明治四十二年二月三日のことであった。その四日後に面接通知が来た。
啄木はその日の様子を日記に「約のごとく朝日新聞社に佐藤氏を訪い、初対面、中背の色の白い肥った麦酒色の髭をはやした無骨な人だった。」「にこにこしながら帰る」に彼の軽い足取りが見えるようである。それから二週間ほどして佐藤氏から手紙が来た。胸を躍らせて開いてみると、「二十五円で校正に入らぬかとあり、夜勤は一夜一円で三十円以上にはなる」とのことで啄木は早速承諾の返事を出した。「東京朝日新聞社」に入社したことは当然家族には通知していたが、三ヶ月過ぎても家族に上京せよという連絡はなかった。啄木にしてみれば、自由に使える金が出来たので、しばらくはのん気に生活をしてみたかったのであろう。 しかし家族にしてみれば、何時までも宮崎氏の世話になっているのも心苦しいことだし、しびれを切らした老母カツは上京を勝手にきめて、啄木にその用意をするように手紙を出した。何の準備もしていなかった彼は、母の手紙を読んであわてた。宮崎氏に現状を報告して支援を仰ぎ、いつものことだと氏は必要な金を送ってくれた。まず家族と住む下宿を決めねばならない。幸い近くの本郷弓町二丁目の新井という理髪店の二階二間を借りることが出来た。そして宮崎氏は家族を同伴して六月十六日の早朝上野駅に着いた。早速家族を案内して新居に入った。これからは定収入も出来たことだし、安心して新生活が出来るはずだが、なかなかそう簡単に事が運ばないのが啄木一家である。 ここで一応朝日新聞社の編集長佐藤北江氏について触れておきたい。啄木は初めての面接であるから、金田一氏から袴をかり、身だしなみを整えて出向いた。名刺を出して、応接間に通され立って待っていると、しばらくして現れたのは色白の太った男性だった。「やあ」というので「やあ」というと、向こうが「私が佐藤」といったから、こちらも「私が石川」といったら、すこし笑いかけて「さあ」と椅子を指したから、初めて自分も腰かけた。佐藤さんも腰を下ろしながら「時にあなたは校正でもやる気がありますか」ときたので、ガッカリしたけど、背に腹は替えられない大朝日だ。「やります」といい自分でアハハと笑ったら佐藤さんもアハハと笑った。この会話からも、おおらかな人物が想像される。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||

