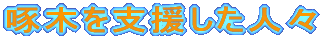
| 6.土岐哀果(2) | |||||||||||
| この歌集「悲しき玩具」は、歌のほかに二題の文章を入れたが、その中の一つが「歌のいろいろ」であった。 この文章の最後に「目を移して、死んだもののやうに畳の上に投げ出されてある人形を見た。歌は私の悲しい玩具である。」この文章は「朝日新聞」に明治四十三年十二月十日から五日間連載されたが、最後に書かれた「歌は私の悲しい玩具である」からとったもので、この文句を採用したのは土岐氏の慧眼だと思う。 何故ならば、啄木は常々歌をおもちゃのようにあつかっていたからである。おそらくこれ以上の題名はないと思うので啄木も満足できるに違いない。この歌集は四十三年十一月から翌年八月にいたる約十ヶ月に作歌された作品百九十二首と別に一枚の紙片に書かれた二首を加えて百九十四首であったが、歌数が如何にも少ないので、前記した文章二作を巻末に入れて体裁を整えた。
土岐氏は歌集編集に際して、「歌稿ノート」に書かれているままを再現すべきだと考えていたと思うが、紙片に書かれていた歌は誰が見ても優れた歌で、土岐氏は迷うことなくこの二首を巻頭にすべきだと思ったのであろう。 呼吸すれば、 胸の中にて鳴る音あり。 凩よりもさびしきその音 眼閉づれど、 心にうかぶ何もなし。 さびしくも、また、眼をあけるかな。 これに対して「歌稿ノート」に書かれていた巻頭歌は 途中にてふと気が変わり、 つとめ先を休みて、今日も、 河岸をさまよへり。 これらの歌を読めば土岐氏の判断が正しかったことが納得されるであろう。「悲しき玩具」という歌集には従来のものと違った特徴がかなりある。それは歌の切れ目に記号を使っていることである。また三行書きを採用したり、三行のうち一行の頭を一字さげるといった字下げなども実施している。しかし啄木は何か新しい試みをしたかったのだと思うが、そうしたことが私などの考えでは読者にとってそう有効な処置であるとは思えない。 また「一握の砂」と顕著な違いをみせるものに歌材がある。その一つは病気の歌で、当時彼には病気の自覚はまったくなかったのだからないのも当然と言えば当然であるが、「悲しき玩具」では四十余首に及び、歌数全体からすれば約四分の一は病気関連の歌がしめていることになる。 貧困と家族扶養とに苦慮する啄木にとって、「あらゆる責任を解除した自由の生活、われらがそれをうる道はただ病気あるのみだ。」とローマ字日記で述べているが、こうした現状からの逃避を病気に求めるという啄木の心情は一般の生活者にはないものであろう。したがって彼の病気の歌は深刻なものにはならないのである。 かなしくも、 病いゆるを願はざる心我にあり。 何の心ぞ。 この歌などがそうした心情を端的に歌ったもので、前記した彼の病気願望をふまえるとよく理解できるのである。 思ふこと盗みきかるる如くにて、 つと胸を引きぬー 聴診器より。 こうした歌を見ても、彼は病気をそう深刻なものと認識してはいないことがわかる。この歌集でもう一つ歌材上での特徴は、家族を詠んだ歌である。「一握の砂」では妻子の歌は十四首であるのに対して「悲しき玩具」では三十一首を数える。こうした変化は病気がその原因になっている。つまり病気によって身体的拘束を受けたために、良い親でも、夫でもなかった啄木の意識が妻子に注がれるようになったのは当然であったと思う。次の歌からその辺りを読み取ることが出来る。
病院に来て、 妻や子をいつくしむ まことの我にかへりけるかな。 また左翼主義に関心を持っていた時期でもあり、そうした歌も見られる。 友も妻もかなしと思ふらしー 病みても猶、 革命のこと口に絶たねば。 この第二歌集「悲しき玩具」は悲しいことに、啄木の死後に出版されたから彼は遂にこの歌集を手にすることは出来なかった。啄木は多くの可能性を残しながら明治四十五年四月十三日午前九時三十分ついにこの世を去った。 四月十五日土岐氏の好意によって彼の生家浅草の等光寺で葬儀が施行された。 当時の状況を翌日の「朝日新聞」は次のように報じている。「やがて会葬者はボツボツ集る。夏目漱石、森田草平、相馬御風、人見東明、北原白秋、山本鼎などといふ先輩やら友人の諸氏が見える。殿には佐々木信綱博士がこられる。それに本社社員を加え淋しい顔を合わせる。人は少ないが心からの同情者のみである。程なく導師土岐月静師は三人の若い僧侶を具して読経する。白衣の未亡人は可憐なる愛嬢京子を携えて焼香した。」以下略。
ここに書かれた人名以外に土岐哀果、金田一京助、佐藤真一といった人達は無論出席していた。 啄木の没後、妻節子は妹光子の世話で、房州の北条に行くことになった。キリスト教関係者のコルバン夫妻が伝道の傍ら、結核療養者の面倒をみてくれるという。節子は本来なら宮崎氏に相談したと思うが、氏とはつまらぬことから絶縁状態となっていたので、頼りにするのは晩年の友人だった土岐氏しかなかった。節子は土岐氏に十三通の書面を送っていろいろのことを相談しているが、収入が無いから氏から二回も送金を受け、彼はそのつど要求に誠実にこたえている。 房州での生活にも行きづまり、土岐氏に送った文面は節子の悲しい心情が語られている。明治四十五年七月七日房州から出したもので、「これは私の本意ではありませんけれど、どうも仕方がありません。夫に対してはすまないけれども、どうしても帰らなければ親子三人うえ死ぬより外ないのです。」そうして函館の親元に帰った節子だったが、結核のため入院先の豊川病院で死去した。大正二年五月五日、二十八歳であった。 土岐氏の啄木にとっての功績は、彼の文学者としての知名度に貢献したということで、それは大正八年「新潮社」に啄木全集を出叛させたことであろう。土岐氏は啄木全集を出すように「新潮社」に交渉したが、当時の啄木の知名度では売れるはずはないので出版社は相手にしてくれなかったが、土岐氏はねばったのである。相手は土岐氏の熱意に負けて、しぶしぶ出叛を承諾した。だが出してみると、予想に反して二十数版も売れたのである。啄木はすでに全国的知名度を持っていたわけで、土岐氏の功績は特筆に価する。 |
|||||||||||
| もくじに戻る | |||||||||||


