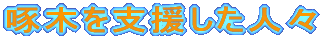
| 6.土岐哀果(1) | |||||||
| 啄木には多くの友人があったが、次第に離れて行き、晩年に親交を持ったのが土岐氏であった。 啄木の日記によれば、「社に帰ると、読売の土岐君から電話がかかった。会いたいといふことであった。とうに会うべき筈のを今まで会はずにいた。そのことを両方から電話口で言い合った。」この二人の最初の出会いは電話であった。 土岐氏が啄木に会いたいと思ったのは、昨年八月「東京朝日新聞」に土岐氏の歌集を採り上げ、好意的批評を発表したことから、一度啄木に会ってみたいと思ったのであろう。それは明治四十四年一月十二日のことであった。
翌日啄木は「読売新聞社」に出向き土岐氏と連れ立って帰宅した。この二人には多くの共通点がある。共に僧家の出であり、新聞社に勤務し、同じ傾向の歌を作ったことや、ローマ字で歌や文章を書き、社会思想などにも関心を持っていた 。したがってこの二人が親密な関係を結ぶのにそれほどの時間を要しなかった。 啄木というのは、気の合う友人とは常に雑誌を出そう、という相談をするが、土岐氏との場合も例外ではなかった。雑誌の表題はすぐに決まった。「樹木と、果実」である。つまり啄木の木と哀果の果を採って命名したのだ。この雑誌の性格について、啄木が尊敬する大島流人氏への書簡で、「表面は歌の革新といふことを看板にした文学雑誌ですが、私の真の意味では、次の時代、新しき社会といふものに対する青年の思想を煽動しやふといふのが目的なのであります。」 「しょっちゅうマッチを擦っては青年の燃えやすい心に投げてやらうといふのです。」といったかなり物騒な雑誌の計画を練っていたのだ。しかし残念なことに、この雑誌は印刷社とのトラブルがあっり、啄木の体調不良などで計画倒れとなり、世に出ることはなかった。 啄木が土岐氏をどうみていたか、日記から引用してみる。「今日は朝から気分がよくて、土岐が来さうな日だと思っていると、果たして午後一時少し過ぎにその土岐がやってきた。私は早速ピラミドンをのんで熱の予防をしながら話した。二人の間には何時逢ってもこれといふまとまった話の出たことはない。しかし私の言ふことには土岐は何でも賛成するし、また土岐の面白がる事は私にも面白い。」と言い、また「土岐は自分自身に苦痛を感ずることなくして人を風刺したり、皮肉ったりすることの出来る人だ。そうしてその頭は明るくて挙動に重くない。」啄木にとって土岐氏は彼がよく使う「我が党の士」に違いない。 前稿でも述べたが、啄木というのはどうしてこうも善意の人に恵まれるのか私などは不思議にさえ思うのだが、この土岐氏なども啄木の最晩年をささえた人物であり、彼の病中から死後にまで及び、啄木のみならず、妻節子も彼を頼り、誠意をもって面倒をみてやった。晩年の啄木から「嫌な感じを受けたことは一度もなかった。」と土岐氏は語っているから、啄木も晩年には反省して、真面目な人間になっていたのであろう。その点土岐氏は幸運なときに付き合ったのだ。 啄木の晩年は自宅の病床で毎日熱との戦いに終始するような有様だったので、病状も漸次進行して快復を望める状況にはないから、何時最後のときを迎えても不思議はなかった。啄木はこれまで、熱心に日記を書いてきたが、二月二十日が最後の記事になった。「日記を付けなかった事、十二日に及んだ。その間私は毎日毎日熱のために苦しめられていた。三十九度まで上がったことさえあった。そうして薬を飲むと汗がでるために、体はひどく疲れてしまって、立って歩くと膝がふらふらする。 そうしている間に金はどんどんなくなった。」「医者は薬価の月末払いを承諾してくれなかった。母の容態は昨今少しいいように見える。しかし食欲は減じた。」これ以後まったくかかれていない。末期の結核だった母かつも、啄木夫妻が全く知らぬ夜中にひっそりと息を引き取り三月七日にこの世を去った。享年六十六歳であった。 土岐氏の厚意により、彼の生家である浅草の等光寺で葬儀を営み、遺骨は同寺に預けられた。この時啄木は自身の命もあといくばくも残っていないことを意識してはいなかっただろう。彼はとにかく金を作る必要に迫られていた。質草になるようなものはことごとく底をつき、さりとて借りる相手もみあたらない。
こんな時頼りにしていた宮崎氏とは、つまらぬいざこざで断絶し、以後金銭的支援は受けられぬ状況になっている。唯一のこされた可能性は歌稿ノート「一握の砂以後」をどこかの出叛社に売ることであった。啄木はかって歌集「一握の砂」を出してくれた「東雲堂」は若山牧水氏の雑誌「創作」も出していることから、若山氏に「東雲堂」との交渉を依頼したが、若山氏と「東雲堂」との間に何か事情があるらしく、若山氏は断って来た。 啄木は若山氏がだめなら、後は土岐氏に頼むしかないと思い、彼に「東雲堂」との交渉を一任した。土岐氏は早速「東雲堂」に出向き、交渉した結果二十円で買い取ってくれた。これが啄木の第二歌集「悲しき玩具」である。土岐氏はその「あとがき」に、「受け取った金を懐にして電車に乗っていた時の心持は、いまだに忘れられない。一生忘れられないだろうと思う。石川は非常に喜んだ。氷嚢の下からどんよりした目を光らせて幾度もうなづいた。」また帰りがけに「石川君は襖を閉めかけた僕に、『おい』と呼び止めた『何だい』と聞くと「これからもよろしくたのむぞ」と言った。 これが僕の石川に物を言われた最後であった。」これは啄木の命が切れる四、五日前のことである。この歌集は「一握の砂以後」とノートの表題には書かれていたが、出版社は前の歌集「一握の砂」とまぎらわしいことを理由に変更を求めたので、「悲しき玩具」を採用した。全歌数は百九十四首であったが如何にも少ないので、「一利己主義者と友人との対話」と「歌のいろいろ」という文章を加えた。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||

