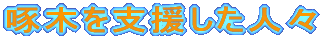
| 4.「小樽日報」の人々(2) | ||||||||||
| 啄木は「小樽日報」の将来性に少々疑問を感じていたから、札幌の小国氏からまた有力な新聞が発刊されるという報告を受けて、沢田編集長には札幌へ行くことを告げて出て行った。もともと小国氏とは話が合うので、つい夜中まで話しこんだのであろう。その日はついに帰社しなかった。 小国氏は啄木より九歳の年長であったが彼とは同県人で岩手県宮古の出身である。氏は地方新聞の発刊に失敗して北海道に渡った。彼は後に独立して「東北海道新聞」を創刊したが成功せずに帰郷して地元の「宮古新聞」で活躍した。
啄木は翌日の夕刻帰社して見ると、小林事務長が待っていた。事務長は沢田編集長に対して、「石川は毎日のように札幌へ行くようだが、社を怠けるとは怪しからん奴だ、事務に届けを出させて下さい。」と、えらい剣幕で怒鳴ってきた。 沢田編集長は越権的干渉だとして、とりあわなかった。しかし常々啄木によい感情を持っていなかった彼は、そう簡単に引き下がるような男ではない。啄木の姿を見るやいなや、たちまち暴力に及び、羽織の紐はちぎれ、額に二つばかり瘤もできた。怒りに紅潮した顔がおかしいので、笑ってやったら、馬鹿にされたと思ったのであろう益々怒ってつきとばしたという。 後に金田一京助氏に語ったところによると、「暴力に対するに暴力をもってしたら、喧嘩は五分五分じゃあありませんか、指一本ささずに笑ってやった方が勝ちですよ。」と言ったというが、金田一氏は手を出さない方が勝ちだという話を聞いていたく感心しているのであるが、啄木は身長一五八センチ、体重四十五キロという女性並みの虚弱体質であるから、手を出しても勝てるはずのないことは本人自身が十分認識しているはずだ。したがって抵抗しなかっただけのことであろう。もし彼が人並み以上の体格を持っていたら、反抗精神旺盛な彼だから、この場合同様の態度をとれたかどうか、はなはだ疑問だと思う。
啄木はその夜すぐ沢田編集長を訪問して退社する決意を伝えた。氏は翌日書面を持って社長に小林事務長暴行事件を報告すると共に、事務長の迅速な処分を要求したが、社長は何の反応も示さなかった。啄木の方に落ち度があると思ったからであろう。啄木は事務長を首にしない限り出社は絶対にしない、と言いその態度は強硬であった。そうこうしてる間にこの年もあと少しを残すだけになっていた。事務長の辞める気配のないことを知った啄木は、社長に退社理由書を提出して決然と去って行ったのである。 この月の給料を手にしたのは、前借分を差し引かれ手取りは十円六十銭でしかなかった。帰途ハガキ百十枚と煙草を買ったら残金は八円少々となった。これが年末の生活費の全てである。常に金には苦労している啄木が、職を失えば生活できないことは十分認識している筈だが、身勝手な彼は後先を考える余裕をすぐに失うのである。 こうして年の瀬を迎えた啄木一家の苦悩は彼の日記に詳しい。「夜となれり、遂に大晦日の夜となれり妻は唯一筋残れる帯を典じて一円五十銭を得きたれり。母と予の衣服二、三点を持って三円を借りる。之をすこしづつ分かちて掛取りを帰すなり。さながら犬の子を集めてパンをやるに似たり。かくて十一時過ぎて漸く債鬼の足を絶つ」このように年末の様子を他人事のように述べているが、啄木はともかく母や節子の心中はいかばかりのものであったろうか。こうして新しい年を迎えても、光明もなければ希望ももてない一家であった。 沢田編集長はそうした啄木一家をみて、函館以来の友人として何とかしなければならぬと思い、社長が兼務する「釧路新聞」への転職を打診することにした。社長は新聞の拡張計画のあることを告げ、啄木の才能を惜しむ気持ちもあったのだろう。「啄木に行ってもらってもいいが彼にも意見があるだろう」という話で、沢田編集長は早速そのことを啄木に伝えた。普通の考えからすれば、勝手な振舞をして自分から去った者の面倒をみる必要はないと思うが、これは沢田編集長の優しさであろう。 それに対する啄木の意見というのは、身勝手なもので、自分に総編集をさせろとか、気に入った知人二名を入れろなど六項目を要求している。社長は笑って「彼の意見書を見るとむつかしい条件があるので考えているのだ」と言う。とうてい全部呑めるような条件ではないことはわかつているから、沢田編集長か中に入って啄木に無理なことをつげて納得させ、結局無条件で釧路行きが決定した。 しかし啄木としては家族の居る小樽を離れたくはなかった。彼は以後も、これまで同様に流浪によって短い人生を終わるのだが、啄木にはまだその意識はなかったであろう。啄木が小樽を発ったのは、明治四十一年一月十九日であった。 子を負ひて 雪の吹き入る停車場に われ見送りし妻の眉かな
啄木は翌日駅前の宮越屋に投宿、日が暮れてから社長も着いた。翌朝六時半の始発でいよいよ最果ての釧路へ向けて社長と共に旭川を発った。 間もなく朝日が昇り雪一色の真っ白の原野を赤々と陽が照らした。当時鉄道網は未発達だったので、釧路まで鉄道が着いたのは前年のことであった。したがって今では考えられないような長時間を要した。帯広に到着したのが午後三時半でここまてでも九時間かかっている。これから先、釧路までは後六時間走るのである。旭川を発って最果ての町に到着したのは厳冬の夜の九時半であった。駅には理事の佐藤国司氏が迎えに出ていた.。 |
||||||||||
| もくじに戻る | ||||||||||


