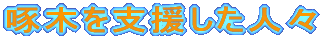
| 4.「小樽日報」の人々(1) | ||||||||||
| 啄木が故郷の渋民を追われて一家離散し、娘光子だけを連れて函館に渡ったのは、明治四十年の五月五日であった。当時函館の文学青年らが出していた同人誌「紅目宿」の依頼で啄木は詩を投稿していた。そうした僅かな関わりであったが、たちまち移転する場所が彼にはなかった。 しかし啄木が函館を選択したことは啄木の人生にとって、文学上また生活上最大の幸運であったということが出来る。
それはここで再び作歌に親しんだことと、経済的支援者宮崎郁雨氏との親交を得たことである。 それはさて置き、啄木はたちまち収入の道を得なければ生活できない。そうしたとき最初に仕事を世話してくれたのが天峰・沢田信太郎氏であった。氏は当時、函館商業会議所の主任書記であり、したがってある程度の仕事を世話することも出来たのであろう。 啄木に与えられた仕事は市内商業者の納税額を写してくる単純な作業であった。その日三百枚ほどを昼飯抜きで処理して帰った。日給六十銭のアルバイトも二十日ほどで終わった。 沢田氏の後に吉野白村氏は弥生尋常小学校の代用教員の職を世話してくれた。月給は十二円であったが、渋民での月収は八円だったから、啄木にしてみれば、これで何とか実家に預けてきた妻子を呼べると考えたのだろう、妻節子が娘京子を連れて函館に着いたのは七月七日であった。 前にも述べたと思うが、宮崎郁雨氏は「函館日日新聞社」に記者として入社させている。とにかく函館の友人達が啄木にそそいだ誠意は、他の土地に移転した場合、同様の好意を獲得できたとは到底思えない。本来ならここで安泰な生活が保障されるはずであったが、啄木の人生というのはどこまでも過酷であった。 函館に移住して三ヶ月過ぎた八月二十五日の夜、東川町の石鹸製造所から発した火は折からの強風に煽られてたちまち大火となって市内の三分の二を焼き尽くし、暁に至ってやっと鎮火した。函館という都市は三方が海に囲まれているという特殊な地形のために、風の強い日に出火すればたちまち大火となるのである。この時の大火は明治時代最大のもので、焼失家屋一万二千三百九十戸、死者八名という函館としては致命的な大惨事であった。 彼の勤務先はことごとく焼失したので函館を出ることになるが、札幌に行っていた友人から「北門新報社」に校正係りの口があるという報告が入った。啄木は迷うことなく札幌移住を決意した。九月十三日、妻子と友人五名に見送られて函館を発った。札幌には同人向井、松岡の二人が迎えに出ていた。当分は向井の下宿に同宿させてもらうこととし、九月十六日に初出勤し給料は十五円であった。 そのころ沢田信太郎氏も札幌に来ていて北海道庁の職員として勤務していた。しかし氏との接触はまだかなり後のことになる。この夜、社の記者小国露堂氏が訪ねてきた。彼はかなりの論客で社会主義者でもあったから、啄木はすぐに意気投合するといった有様で、その日の日記に「小国君のいう所は見識あり、雅量あり、小国君は我党の士なり」と述べている。
それから数日後の夜、小国氏が訪ねてきての話に、今度小樽に新しい新聞「小樽日報」が創刊されるという情報があるが、乗り換えてはどうか、という相談であった。休刊中の「北鳴新聞」の記者であった童謡詩人野口雨情氏にもすでに声をかけていて参加するとの確約をえているという。啄木は小樽ならば姉夫婦のもとに妻子も同居していることだし、新しく創刊される新聞というのも魅力的だったと思うから三日後に小国氏を訪問して小樽行きを伝えた。札幌には十日余り滞在したに過ぎずこの月二十七日には妻子の待つ小樽へ発つた。 この新聞は山県勇三郎氏が社主で道会議員の白石義郎氏が社長であった。白石氏はこれ以外に「釧路新聞」の社長も兼務しているという、なかなかの人物であった。社はまだ木の香の残る新築の社屋であった。翌日早速出社して岩泉江東主筆に面接し、四日後の十月一日に初の編集会議が開催されることを告げられる。会議当日の模様を啄木は日記に次のように綴っている「予は最も弁じたり。出席したる者白石社長以下八名。予は野口君と共に三面を受け持つこととなれり。夜精養軒にて一同晩餐を共にし、麦酒の杯をあげたり。」
こうして新聞記者の生活が始まったが、同業の野口氏はかねてから他社時代に岩泉主席と個人的にトラブルがあったらしく、主席は前科三犯だとかといった話も出て、こうした人物の下では働けぬと言い岩泉主席排斥の運動か始まった。しかしこの計画は事前にもれ、首謀者の野口雨情は遂に退社して行った。 しかし社長は社内の状況や編集などにも不満を持ち主筆岩泉氏も解雇した。その後に、啄木の推挙した沢田信太郎氏を入社させたのである。沢田氏が偶然啄木を訪ねたのか、啄木が彼を呼んだのかは定かではないが、とにかく突然「小樽日報の編集長を引き受けてはくれまいか」という話がでた。「返答に窮したが話している内に、啄木の情熱にほだされて、彼と協力して立派な新聞を作ることに以上な興味を覚えるようになり、会談四時間にして遂に彼の要求に応じて入社を承諾した。」と沢田氏は入社の経緯を述べている。啄木にしてみれば強い味方が出来たので少々のミスをしても安泰だと考えたに違いない。 啄木というのはその生涯において、少し慣れると自分勝手な行動が多く、渋民での代用教員時代、無断欠勤して小説を書くことが多々あった。教員の少ない田舎の小学校ではその穴をうめるのに苦心したことだろう。自分の考えが最優先で人に迷惑をかけることなど、殆んど彼の意識にはないのだ。つまり一般の常識というものがわかっていないのか、あるいは無視しているかであろう。 |
||||||||||
| もくじに戻る | ||||||||||


