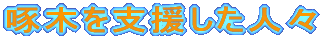
| 3.啄木と小田島尚三(1) | ||||||||||
| 啄木は短歌ばかりではなく、詩にも強い関心を抱いていたから、何時短歌から詩作に転換しても不思議ではなかった。これまでも内外の詩集に目を通し、「明星」でも、社友の詩に親しんできた。したがって詩に対する自己の考えはすでに確立していたのだ。 蒲原有明といえば当時の大家であるが、彼は中学五年生の時、有明の詩集「草わかば」についての評論を「岩手日報」に発表している。この文章で見る限り、とうてい少年の筆とは思えない、大人と対等の立場で書いていることがわかる。例えば「新体詩新創以来有数の作である。」とか「着眼面白し、結末の一聯出色の文字」また「有明氏に対する希望は二つある。と云ふのは、用語を選択して文学上の晦渋をさけることと、一つは構想取材の範囲を拡張して貰ひたい事である。」とあり、こうしたことが堂々と言えるのは誰が見ても啄木の詩に対する水準が並みのものでないことが理解されよう。
だが啄木は短歌を続けていたが、明治三十六年十一月初め突如として詩作に転換したのである。その動機については従来、「与謝野鉄幹説」が有力であった。鉄幹氏は「啄木君の思い出」という文章の中で、啄木の歌について次のように述べている。 「その頃の啄木君の歌は大して面白いもので無かった。それで私は他の友人にも云ふやうに思ひ切った忠告を書いた。『君の歌は何の創新も無い。失礼ながら歌を止めて、外の詩体を選ばれるがよからう。さうしたら君自身の新しい世界が開けるかも知れない。自分はこの事を君におすすめする。』といふ意味の手紙を盛岡へ送ったのであった。」と言うが、しかし私はこの記述に疑問を持っている。与謝野氏は「明星」の明治三十六年十二月号の合評会で、啄木の歌八首のうち、六首は私の好きな歌だとし、その中の二首は傑作だと推奨しているのである。啄木の歌が初めて「明星」に一首掲載されたのは、前年の十月であった。「血に染めし歌をわが世のなごりにてさすらひここに野にさけぶ秋」という歌である。 以後号を重ねるにつれ歌数も増加し、翌年の十月には「新誌社」の同人に推挙されている。この間ただの一年でしかない。この事実は啄木の実績と将来性を認めたからに相違ない。このような状況にある啄木が、なぜ歌を止めて他の詩体を選ばねばならないのであろうか。与謝野氏の言われることは矛盾している。したがって私には「与謝野説」は説得力がない。
突然歌から詩作に転換した原因を、私は野口米次郎氏の第三詩集「東海より」を啄木が読んだ時からだと考えるのである。この詩集は英国で発行されたものだが、「富山房」はこの年十月、日本版として「東海より」を出版した。彼は新聞広告でその記事を見たのだが、その時注目したのは野口氏が米国に在住している詩人だということであった。というのは、当時啄木はかなり強い「渡米熱」を持っていたからである。 私が詩に転換したのを突然と述べたのは、「明星」の十二月号には既に短歌の原稿を送付済みであったからである。この詩集「東海より」を節子が啄木に贈ったというが、彼女が自身の判断で購入して送ったとは思えない。野口氏は当時まだ国内では無名の存在であったし、節子が著名な歌集ならともかく、詩に対する知識はそうなかったと思うからである。一方啄木は野口氏に接近することによって、渡米の情報なり援助を受けられるのではないかと考えたであろう。是非この詩集を読みたいと思っても、当時の彼には余分な資金はなかった。それは野村長一氏への書簡で証明出来る。「生は兄に借財しているが其の後、本代も何も薬代と変じて相不変、失敬している。誠に面目ない次第である。」という。啄木は節子に支援を仰ぐしかなかった。彼女は愛する彼のために、至急に購入して贈ったものと考える。「富山房」が「東海より」を出版したのは十月であったから、早ければ十月中、遅くとも十一月初旬には、啄木は読んだと推測される。 啄木は「東海より」に感動し、野口氏に接近するためには、詩の実作を用意する必要を感じ、十一月の初旬から急遽詩作に入ったのである。「明星」の十二月号にはすでに従来どうり短歌の原稿を送っていたから、本来なら詩の原稿は一月号に出せばいいと思うが、彼は焦っていたのだろう、十二月号に短歌と共に「秋調」と題し五作の詩を載せたのである。詩には初めて「啄木」の号を使った。詩はおおむね好評であった。 野口米次郎氏は明治八年の生まれであるから、啄木より十一年の年長である。彼は十八歳のとき単身渡米し、苦労しながら詩集二冊を出し、英国へ渡って出版したのが第三詩集「東海より」であった。
この年十二月に入ると啄木は「詩談一則」という「東海より」の評論を書いた。「之を読む事、幾許ならずして幽妙の詩趣誌上に溢れ、胸底朗然として清興また一点の俗念を止めざるに似たり。」また「独吟して深く氏の詩風を愛する者、この感懐を談じて新春の読者にわかたんとす。」と述べ,各詩にそれぞれ好意ある感想を加えた後、「野口氏は明らかに我が日本の光栄なり、国内の詩潮未だ全く定まらざるの日に於いて、異土の文園にこの成功を見るをえたるは、吾人同胞の大いに意を強うする所。」と持ち上げて、この論文は「岩手日報」に投稿され、新年の紙面を飾ったのである。この掲載紙は当然野口氏にすぐ送り、後で自分の詩稿も送ると書いている。これで準備も整ったと考えた啄木は、野口氏に長文の手紙を出した。 この手紙は明治三十七年一月十一日に発信された。「大兄の導きだした詩の巨鐘の、哀れむべき一青年に及ぼしたる余響は、単に詩興一面の感化ではなくて、私が幼児より心掛けていた米国行きの希望に、強く制すべからざる加熱力を与えたのであります。ここに至って大兄に対する私の敬慕は一層深い感謝と共に胸の中に燃えているのです。たとえ如何なることがあっても、私是非この望を果たさなくてはならぬ。」また「なつかしい大兄の高風に接すべく、如何にして己が渡航の機会、否費用をみつけたらよいであらうか。」と書き、この文章の最後に啄木の本音が覗いている。 つまり金の無い彼としては野口氏から渡航費用をなんとかして引き出せないか、という考えが強くあったと思う。野口氏の作品をベタ褒めしているのもその為のような気がする。これまでの流れをみると、「東海より」を読んだ時点から短歌を中止し、即座に作詩に入り、評論を「岩手日報」に発表したり、原稿用紙八枚に及ぶ長文の手紙も送っている。つまり詩作に転換して以後すべて野口氏に関係しているのを見ても、詩への転換動機は「東海より」を読んだ結果だと断定できる。したがって「与謝野鉄幹説」などは関係ないことがわかる。 しかしいくら待っても野口氏からは何の返事もなかった。野口氏もやっと名がでた時で、余裕ある生活者ではなかったからだろう。 |
||||||||||
| もくじに戻る | ||||||||||


