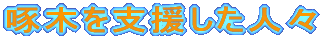
| 2.啄木と宮崎郁雨(6) | ||||||||||
| 一般に「不愉快な事件」とか「晩節問題」などと言われているこの問題についての概略は前に述べたので了承されたものと思う。 しかし困ったことに、光子、丸谷両氏の記述を信じて、郁雨、節子両氏にやましい関係があったかの如き記述をする研究者もあるのだ。この件は郁雨、節子両氏の名誉に関わる問題であるから、黒白を明確につけておく必要があると思うので、以下私見を詳述しておきたい。 この問題について触れる人の多くは郁雨、節子両氏の性格なり人柄から、不貞といったことについて否定的であるが、中に肯定する論者もいるのである。石井勉次郎氏などがその例である。
石井氏の記述を引いてみよう。氏の著「私伝・石川啄木・暗い淵」は郁雨、阿部たつを両氏の論を糾弾する事にかなりのページを割いているが、私などが同感出来る記述ではない。 で、氏の肯定論は次のようになっている。「真相暴露に立ち上がった三浦光子の公表文書はすべて中傷論として葬り去られ、長い間『臭い物には蓋』の状態だったが、ついに丸谷喜市の『覚書』が発表され『匿名の手紙』が、たしかに存在したこと、しかもその内容がラブレーターであったことが証明されて、ようやくこの問題に終止符が打たれた。」 石井氏ほどの学者が、丸谷氏の出鱈目な記述を何の疑いも持たずに信用されるのが、私は不思議にさえ思うのである。この「覚書」にしても、「従来の不毛の論争に終止符を打つ重要な文献であり、厳正にして簡潔な報告であるから、とくにその全文を引用しておく必要がある。」としながら、阿部氏に丸谷氏が返信として送った「覚書」の原文は引かず、なぜかその後「大阪啄木会」の機関紙「あしあと」に発表された方を引用しているのである。私が重視している点で阿部氏には「手紙は読まなかった」ことを強調しながら、「あしあと」には「他人の手紙は成るべく読まないと言ふことが私の方針であった。」という部分を抹殺し「私はざっと愚目するに止めた」と書き直しているほうを採用しているのである。これは自己都合によってそうしたのであろう。「読まなかった」では説得力に欠けると判断したに違いない。
手紙の差出人にしても、光子は匿名だとし、丸谷氏は三文字だったという。郁雨氏は匿名ではないと言っている。それは当然で、丸谷氏でさえ一見して郁雨の字だとわかったものが、よく文通していた啄木や節子に解らぬはずはない。従って、匿名になどする必要はないのである。 光子や丸谷氏の記述が出鱈目なのだ。したがって私は、こうした虚偽の記述についてコメントすることもないと思うが、啄木の生涯を述べる場合、多くの論者はこの問題について必ず何らかのコメントをしている。 したがって私も郁雨氏に関係する事項であるから、少々詳しく私見を述べて見たいと思う。 この件の切っ掛けになった文書は前記したように、光子夫妻が阿蘇にいた当時、「九州日日新聞」に、大正十三年年四月十日から十三日にかけて「兄啄木のことども」という文章を発表した。その最後にある「最後の痛手」という記述が問題であった。 「十三年の長い間私は沈黙していました。けれども之は余りに苦しい沈黙でした。私はもう沈黙は出来ません。大いなる悲しみと、大いなる怒りとが込み上げて参ります。」そして「嗚呼啄木はその手紙を読まねばよかった。若し彼がその手紙に眼を触れなかったならば、彼は愛妻の手厚い看護に守られつつ苦しいけれども平安な死の眠りに就いたであらうものを、思へばその一枚の書信こそ彼が生命をとした恋の仮面を引きむしるものであったのだ。すべての事がわかったのです。妻は他に愛人を有していました。なんたる呪はしいことでしょう。」少々長い引用になったが、この文章のなかで、私が疑問に思ったのは二点ある。 その一点は、不愉快な感情というものは、日時の経過と共に次第に希薄になって行くものだと思うが、光子は十三年も経過した時点で、まるで近年のことのように憤っている。 二点目は、この事件というのは、郁雨、啄木、節子の三者に関わる問題であって、光子にはまったく関係はない。 なぜ光子が十三年もたった時点でこうした問題を発表したのかについて、郁雨氏が節子に出した手紙以外に光子を憤慨させる事項があったのではないかと私は考える。 それで思い出すのが、啄木一家の遺骨と墓の問題である。節子は母かつから結核をうつされて函館に帰った頃かなり病状も進んでいたから、豊川病院に入院して療養中であった。 彼女の心に残っていたのは、東京の寺に預けてきた、真一、啄木、母の遺骨であった。節子は、郁雨氏に相談し、函館図書館長の岡田健蔵氏に上京して遺骨を持ち帰ることを依頼した。 小樽の山本家に身をよせている一禎和尚に、とにかく石川家の当主であるから一応遺骨の処置について、節子の父忠操氏が懇切丁寧な書簡を送って一禎氏の考えを待ったが、彼の返事は意外なものであった。「そちらで適当に処置するように」といったまるで他人事のような返事だった。すぐ墓は造れなくとも、身内の遺骨は自分の手元におけるのである。 函館の友人達は憤慨し、墓は断然函館に建てるという決意で固まった。遺骨をそのままにして置くわけにも行かず、啄木が愛した大森浜を一望にする立待岬に簡単な杭を立てて葬った。この問題を解決する場合、大正十三年という時期が重要である。それは、この年に函館で、本格的な啄木墓碑建設の具体案が発表されたのである。
この報告を聞きつけた光子は、私に相談することもなく、石川家の遺骨を勝手に函館に集め、恒久的な墓碑まで造ろうとしている。彼女の怒りというのはここにあるわけで、「不愉快な事件」とか、節子の「晩節問題」などという郁雨氏が節子に送った返事の手紙などはこの件には全く無関係なのだ。ようするに節子が郁雨氏に計って、墓碑建設をこの二人が計画したと考え、大正十三年に光子は故郷ではなく、函館に墓を建てることに我慢ができず、この二人に不純な関係があったかのごとく、報復する意味で、でっち上げた文章を熊本の「九州日日新聞」に発表したというのが、真相ではないかと私は思っている。 函館の墓碑建設についての当事者は、一禎和尚に「遺骨の処置」について相談し、「そちらで適当に処置するように」という許可を得て事にあたっているのだから、また学生であった光子に相談する必要はない。もし父一禎和尚が遺骨を引き取っていれば、こうした問題は起こらなかったのである。だから光子の怒りは父一禎和尚に向けられるべきものであろう。 この件以前までの光子は、郁雨氏や節子とは良好な関係にたったから、光子の言う「晩節問題」などをまともに取り上げる研究者は、光子にもて遊ばれているような気がするのである。 |
||||||||||
| もくじに戻る | ||||||||||


