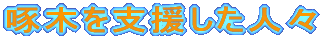
| 2.啄木と宮崎郁雨 (4) | |||||||
| しかし考えてもいなかった大火災によってその期待は費えた。 もしこの大火がなかったら、啄木は釧路のはてまで流浪する必要はなかったのである。この一家の心情としては、折角落ち着いたと思ったのも束の間で、再び漂泊の身に落とされたのであるから、彼らの心情を考えるとき、心からの同情を禁じえないが、私はこの状況を招いたことが悪いばかりではなかったと考えている。 何故ならば、函館から釧路までの流浪によって、数々の秀歌をものしているからである。これは歌集「一握の砂」の成立にとってはなはだ重要である。 歌集の巻頭に、 東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる。
これら北海道の歌群は歌集にとって重要な位置を占めていることについては異論がないであろう。 歌集「一握の砂」で重視すべき歌群はふるさとを歌った「煙」と北海道の「忘れがたき人々」であると思うが、試みに、北海道の歌群をこの歌集から削除すれば、「一握の砂」の魅力は半減すると思う。しかも橘智恵子や小奴を歌った歌群はこの歌集に彩を添えている。こうした歌は「煙」には無い歌であることを思えば、北海道歌群の重要さがわかると思う。 啄木は四月五日に釧路を脱出し再び函館に帰った。郁雨氏との話で、「上京したい希望があるなら家族は当分面倒を見るから、」との申し出があり、彼は即座に東京行きを決意した。四月二十四日には早くも函館を発った。収入のない家族だから、住まいから、生活費まで全て郁雨氏の負担になるわけで、そのようなことを引き受ける者は他に居るはずは無い。 郁雨氏だから出来るのである。こうした点を見ても、啄木が函館に来て、郁雨氏と親交を持ったことが、如何に大きなことかが解る。 啄木が上京してひと月ほど立った頃、娘京子が発熱し、ヂフテリヤで重態だという連絡が入った。郁雨氏はその時の心情を次のように述べている。「あの時は本当に当惑した。夫の留守中瀕死の愛児を看護する節子さんの哀情を偲び、家族を預かる自分の責任を思って、共々に夜を徹して看病した日もあったが、九死に一生を得ることが出来た。」 郁雨氏の心情は察するに余りがある。流石の啄木も京子の病気にはかなりのショックを受けたようだ。日記に「予の頭は氷をあびせられた、京子の昏睡」「節子の心と友の情けだけでもきっと治る。友はきっと癒すと書いてよこした。妻の心を思うと涙が落ちた。」幸い京子は治癒したとの連絡が入って啄木も安堵した。 函館に残された家族は、啄木もやっと一流の「毎日新聞」に小説が出るようになったことだし、「朝日新聞社」への就職も出来たのだから、間もなく上京せよとの連絡があるものとばかり思っていたが、なかなか来ないので、母親はしびれを切らし、勝手に上京を決め、啄木にその準備をするように手紙を出した。 啄木にしてみれば、もう少し気ままに暮らしたかったと考えていたようだから、少々慌てて下宿を探し、郁雨氏に移転費用を送らせた。郁雨氏にしてみれば、母が上京することを聞いた時に、当然啄木の了承を得ているものと思っていたが母が独断で決めたのだ。郁雨氏は家族を伴い、六月七日に函館を発った。 その頃啄木は名作「ローマ字日記」を執筆していたが、家族の到着した日が最後になった。 最後の記事は「十六日の朝、まだ日の昇らぬ内に、予と金田一君と岩本と三人は上野のステーションのプラットホームにあった。汽車は一時間遅れて着いた。友、母、妻、子、車で新しい家に入いった。」以後日記は翌年まで書かれていない。 ここでちょっと歌集「一握の砂」に触れておきたい。郁雨氏は、「函館日日新聞」に歌集の書評を連載し広告も出してやった。啄木は早速感謝の気持ちを伝えてきた。「君が真向から書いてくれるのが何より気持ちがいい、何しろ歌集を二号表題で批評するということが、明治の新聞に未曾有なことだ。況んやそれを何日も何日も続けるということをやだ。」また「僕はやっぱり死ぬ時は函館で死にたいやうに思う。」函館の友人達が彼に惜しまぬ支援を与えたことが、こうした言葉になったのであろう。しかし彼の願いも空しく東京で命が切れ、函館に帰ることはなかった。 話は違うが歌集「一握の砂」の扉に、献辞を書いている。 函館なる郁雨宮崎大四郎君 同国の友文学士花明金田一京助君 の両君に捧ぐ
だがしかし、私の考えは少々異なる。郁雨氏は啄木の生涯にわたって経済的支援を与えた。その金額は半端なものではない。郁雨氏以外の者でこうした支援の出来る者は絶無であろう。従って啄木にすれば第一に郁雨氏を据えたのも理解できる。しかしその金は郁雨氏自身が作った資金ではない。実家が裕福だったから出せた金である。 その点、金田一氏の場合は全く違う。彼は中学の教師をしていたサラリーマンにすぎない。当時の給料は三十五円であった。彼一人の生活ならば、下宿代十五円を支払っても、後に二十円残るのである。この金額で生活費としては十分であった。だが啄木を同居させた場合を考えると、手元に残る金は五円程にしかならないのである。こうした犠牲を払ってまで、啄木を支援する人は金田一氏だから出来たのであって、彼以外に出来る人物はまずないと思う。 郁雨氏と金田一氏とでは立場がまったく違っていることがわかる。郁雨氏が個人で働いて得た金ならば金田一氏と同列に出来るが、そうではない。したがって私は、中学の先輩でもある金田一氏を上位に置くべきだと考えるのである。これは啄木の歌集であるから、他人がとやかく言う必要はないから、これくらいにして次に移ろう。 啄木の体調も漸次悪化していく中で、また問題が起こった。一般に「不愉快な事件」と言われている。これは郁雨氏が節子宛に出した手紙が啄木の目に触れて問題になった。しかし不思議なことに、それは啄木が死亡して十三年も経った大正十三年以後のことである。啄木の妹光子が大正十三年当時熊本の阿蘇に暮らしていたが、地元の「熊本日日新聞」に、四月十日から十三日にかけて連載された。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||

