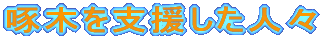
| 2.啄木と宮崎郁雨 (2) | |||||||
| だが郁雨は本音として「しかし私は、それとなく胸中に描いていた節子夫人像とは、かなりに違った現実の本人を目前にして、軽い失望を心中に感じていた。」ということは、啄木がよほど彼女を美化して語っていたか、郁雨氏が勝手に絶世の美人とでも想像していたのであろう。 だが失望とは書いているがそれは外見に対する郁雨氏の第一印象であって、人格や性格あるいは人柄についてではない。日時の経過と共に、節子の日常を観察しているうちに、彼は次第に尊敬の念を抱くようになるのである。 同人達は何一つ持たない啄木一家のために、各自の家から家財道具一切を持ち寄って住まわせたのである。 啄木は日記に、「この日青柳町十八番地石館借家のラの四号に新居を構へ、友人八名の助力によって、ともかくも家らしくとり方づけたり。予はまた一家の主人となれり。」といってやっと落ち着くことが出来たまではいいが、「宮崎君あり、これ真の男なり。この友とは七月に至りて格別の親愛を得たり。」といって早速葉書で借金を申し込んでいる。
「昨日の御礼申し上げ候。お陰にて人間の住む家らしくなり候。懐中の淋しきは心も淋しくなる所以に御座候。申し上げかね候へども実は妻も可哀相だし、○少し当分御貸し下され度く奉懇願候、少しにてもよろしく御座候。」この文面に対して、郁雨氏は、「彼の手元に必要なだけの金がないことも大よそ解っていたので、「私は少し苦笑しながら直に出向いて十円か十五円か置いてきたという。啄木は友人の殆どが勤務者であることを知っていたが、郁雨氏だけは手広く味噌の製造販売をしている商家の若旦那であることもわかっていた。そこに目をつけて郁雨氏に借金を申し込んだのだ。これが将来に渡って続く最初の借金であった。 啄木から申し出のあった時ばかりではない。この一家には常々気をつけていたようで、「ある日『一体食う米があるのか』と聞いてみた。彼はあの底光りのする眼球を一寸の間うろつかせたが、節子さんを顧みて『あるか』と聞いた。節子さんは顔を赤くして『ごあんせん』と答える。彼は流石に少してれくさい表情で『ないそうだ』と私に言った。」郁雨氏は帰り際にそっと節子に金を渡した。 父竹四郎氏という人物は、故郷の旧家に生まれながら、彼は没落した家の再興に勤めたが再起出来ず、単身北海道で土方までして貧困の体験に耐えた経験を持つだけに貧者には常に愛情を持って接していた。というのも実弟の証言によれば、「私の実家では父竹四郎存命の時代には函館の大森町に乞食部落があり、その乞食が毎日市内に物乞いに出るのであるが、夕方部落に帰る途中必ず数名の乞食が代わる代わる私の実家に立ち寄るのである。父はその乞食等に飯を食わせ、寒い時は焚火をして体を温めてやった。」という。 また「長兄が啄木一家の困窮を救うために、物心両面にわたり友情を尽くしたことは当然のことである。」そして「自分の幸福は他にも分かち与えよ、というのが宮崎家の家憲である」と述べている。こうした家庭で、父の背中を見て成人した郁雨氏だから、ただの「お人好し」などとは次元の違うことが実弟の証言からも了解出来るのである。 啄木の学校における勤務状態に不安を抱いていた郁雨氏は、万一のことを考えて彼の知人である「函館日日新聞社」の主筆斎藤大硯氏に依頼し、小学校の方はそのままにして遊軍記者ということで入社させた。啄木にとって堅苦しい小学校よりは新聞社のほうが自由もあり、彼の性分に合うのであろう。入社草々、「歌壇」を設けたり、評論を書いたりして熱心に仕事に打ち込んだ。 その頃、郁雨氏は、重砲兵将校の資格習得のため、この年八月一日から九十日間軍隊生活に入った。 啄木の生涯を通観して見る時、渋民の寺を追われてから、割合楽しく安泰の生活が出来たのは、短い期間ではあったが、この函館ではなかったかと思う。 しかしこの安泰な生活も突然奪われる事態が発生した。八月二十五日夜、東川町の石鹸工場から出火した火は、折からの強風に煽られ、たちまち市外の三分の二を焼き尽くし、暁にいたってやっと鎮火した。焼失家屋一万二千三百九十戸という大参事となった。函館はもともと大火の多い町で、三面海に囲まれているという特異な地形から、市内は吹き曝し状態になり、火の回りも速く大火になりやすい。明治時代だけを見ても百戸以上焼失したのが十九回もあり、その内千戸以上の焼失は六回を数える。
その中でも四十年の大火は最大のものであった。幸い、啄木と郁雨氏の家は類焼をまぬかれた。しかし「弥生小学校」や「函館日日新聞社」も共に焼け落ちたので、啄木は全ての勤務先を失ったのである。 彼はこうした大火などに遭遇したのは初めての経験だったと思うので、彼の感想を日記から引いてみよう。「市中は惨状を極めたり。町々の処々に火の残れるを見、黄煙全市の天を覆ふて天日を仰ぐ能はず。狂へル雲の上には、狂へる神が、狂へる下界の物音に浮き立ちて、狂へる舞踏をばなしにけむ。予は遂に何の語を以って之を記すべきかを知らず。火は大洪水の如く街を流れ、火の粉は夕立の雨の如く降れり、全市は火なりき。」この記述は、そうした経験を持ったことのある人ならば同感出来ると思うが、その後の記述は同じ人物が書いたとは考えられぬたぐいの記述である。 「高きより之を見たる時、予は手を打ちて快哉を叫べりき、予の見たるは幾万人の家を焼く残忍の火にあらずして、悲壮極まる革命の旗を翻へし、長さ一里の火の壁の上より函館を覆へる真黒の手なりき」「かの夜、予は実に愉快なりき、愉快といふも言葉当らず、予は凡てを忘れてかの偉大なる火の前に叩頭せむとしたり、一家の安危豪も予が心にあらざりき、幾万円を投じたる大高楼の見る間に倒るるを見て、予は寸厘も哀惜の情を起すなくして、心の声のあらむ限りに快哉を絶呼したりき。」 ここには勤務先や家を失った被害者に対する憐憫の情などは全くない。「一家の安危豪も予が心にあらざりき。」と言うのだから、啄木というのは、非情な人物だと言われても仕方がない。 彼は札幌から帰ってきた向井氏に履歴書を託し、札幌での就職を依頼した。向井氏からは間もなく「北門新報社」に校正係りの口があるという連絡があり、啄木は即座に札幌行きを決めた。 彼が札幌に向け家族や友人達に見送られて函館を発ったのは明治四十年九月十三日であった。啄木はまあいいとしても、妻節子が、七月に来て九月にはまた別れ別れの生活を強いられるという心中を思うとき、私は同情を禁じえない。 函館では五ヶ月足らずの生活であったが去るにあたり、この土地に多くの思い出を残していた。しかし近日再び漂泊の身として此処を去らねばならないのだ。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||

