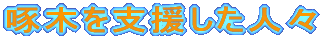
| 1.啄木と金田一京助 (5) | |||||||
| その節子が家出するなどということを啄木は思ってもみなかったであろう。彼の考えが少々甘かったのである。それだけに、そのうろたえ様は尋常ではなかった。直ちに金田一氏の所へ飛んで行き、彼の支援を求めた。 「戻ってくれなければ私は生きておれない。頼るのは貴方一人です。どうか戻るように手紙を出して下さい。」と懇願した。「私が可愛そうだと意気地なく泣いているように書いてもよいし、私を何と書いてもいい。」この有様はまるで無条件降伏である。常に戦闘的態度の啄木だと思うが、裏を返せば案外情けない、弱い彼の姿が見えてくる。これは夫婦間の問題であるから、一般的に言えば、夫婦で話し合って解決すればいい問題であろう。他人に解決を願うことではない。
しかし金田一氏は即座に啄木の頼みに応じ、「私は長い長い手紙を、仕舞には、自分の妻にでも逃げられたように、ボロボロ涙を落としながら書いて出した。これなら帰らずにはおれまい、と思うような名文を書いたつもりだった。」〈石川啄木〉 啄木はまだ不安だったのか、盛岡高等小学校時代の恩師、新渡戸仙岳氏にも書簡を送り、クドクドと家出の経緯を述べた後、「一日も早く帰ってくるよう御命じ被下度伏して願い上げ奉り候」とある。 節子にしてみれば、啄木がこれほどなりふりかまわず慌てるとは思わなかっただろう。自分が出ていって一番困るのは母かつなのだ。家事一切がのしかかってくるからである。この際少し苦しめてやれば反省する機会にもなるはずだ、といった節子の考えもあったように思う。また身勝手な行動に終始し、家族に対する思いやりに欠ける啄木にも良い反省の機会になるだろう。 啄木が離縁を申し渡したのなら別だが、節子には離婚する意思はなかったと思う。なぜならば、結婚に際して、絶対反対する父をふりきってまで啄木のもとへ嫁いだ強固な意志を持つ彼女だったから、金田一氏がどんな名文を書いたとしても、今更駄目でしたと言って、実家へ戻れるはずはなかった。節子は二十四日ぶりに東京へ帰ってきた。 啄木は前年夏以来次第に体調を崩して発熱を繰り返し、遂に最後の年となる明治四十五年を迎えた。彼は日記に、「私の家は病人の家だ、どれもこれも不愉快な顔をした病人の家だ。俺の家の者が皆肺病になって死ぬことを覚悟しているのだ。」母は誰も知らぬ夜中にひっそりと息を引き取った。 当時の状況を金田一氏は、「彼が亡くなる十日前に行って見ると、想像にも及ばない気の毒な状態にあった。石川君はその時『ひょっとしたら自分も今度は駄目だ』と言った。『医者は』と聞くと、『薬代を滞るものだから、薬もくれないし、来てもくれない』そしてまた『いくら自分で生きたいと思ったって、こんなですもの』と言って、自分で夜具の脇を空けて腰の骨を見せた。ぐっと突っ立った骨盤の骨、髑髏の両脚を誤ってあばいたような恐ろしい驚きに、私は覚えず怖いものに蓋をするようにして、『これじゃあいけない、滋養になるものを食べて少し肥るようにしなくっちゃあ』と言ったら、『それどころか米さえない』と顔を歪めて笑った。」 金田一氏は急いで自宅に戻り、生活費から十円を抜きとり啄木のもとへ引き返した。「少しですが」と遠慮がちに渡したら、啄木は寝たまま片手で拝むようにした。節子は下を向いて涙を落とした。 それから十三日過ぎた早朝のことであった。車屋にひどく門をたたかれ出てみると、「小石川の石川さんからです。すぐこれに乗って、」という迎えだった。啄木は金田一氏の顔を見るなり「たのむ」といったきり目を閉じた。金田一氏にしてみれば、彼の死後家族をよろしく頼むという意味にうけとったと思う。その後若山牧水氏も呼ばれて駆けつけた。金田一氏は出勤時間が来たので、後は若山氏にまかせて席を立った。それから三四十分過ぎたころ啄木の様子が急変した。 啄木は遂にこの年四月十三日午前九時半、二十六年二ヶ月という若さで、多くの可能性を残しながら天国へ召された。 私はこれまで、その時々の支援者を見てきたが、金田一氏ほど多くの犠牲を払ってまで、啄木の面倒を見た人はいない。それに対して啄木は、表面的には前記したように、「死んだら貴方を守る。」とか「金田一といふ人は世界に唯一の人である。決して世に二人とあるべきではない。」というような一応感謝の言葉を述べているようだが、私の印象では心からそう思っていたのかどうか、少々疑問を持つのである。 と言うのは「ローマ字日記」に次の記述があるからである。「一方金田一君は、弱い人のことはまた争われない。人の性格に二面あるのは疑うべからざる事実だ。友は一面、まことにおとなしい、人の良い、やさしい、思いやりの深い男だと共に、一面嫉妬深い、弱い小さなうぬぼれのある、めめしい男だ。」これは啄木の心底にある金田一観に違いない。 金田一氏の支援がなかったら、啄木の東京生活は草々に破綻していたのだから、そのことを考えれば、「ローマ字日記」に彼を不快にさすような記述をする必要はない。この金田一氏の記述がなくとも、「ローマ字日記」の評価には全く関係がないと思うので、恩人を誹謗するような記述は常識のある人なら避けたであろう。
啄木というのは、文学面はともかくとして、生活者としてみれば非常識な面が多々あり、返済不能の高額な借金を抱え、ただ借金地獄から逃げ出すことしか考えず、返済の意思さえない男が、反省をすることもなく、言うことだけが達者と言うのでは、他人の欠点をあばくような資格はないと私は思う。 そうした啄木ではあったが、金田一氏は啄木をかばう行為はあっても、彼を糾弾するようなことは生涯なかった。 金田一氏の記述の中で、唯一岩城之徳氏と論争となったのが「啄木逝いて七年」という文章であった。問題の部分を引くと、「石川君の病が一時小糠を得たことがある。それは四十四年の夏から秋へかけての事だったと思う。その間に一度杖につかまって私の家まできてくれた。」この部分と「私の思想については随分御心配をかけたものだがもう安心してください。」「しいて呼べば社会主義的帝国主義ですなあ」最初の問題は、啄木がはたして金田一氏を訪ねたかであるが、この当時啄木の体調は悪く、発熱をくりかえしていた。つまり病人だった。啄木の家と金田一氏の家との距離は約三キロあった。杖をついてというから徒歩であろう。訪問できるような体調ではない。また社会主義的帝国主義といった思想も理解できない。 油と水を一緒にするようなものだから、私は金田一氏が啄木を社会主義者にして置きたくない、という心情がこうした文章を書かせたのだと考えている。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||

