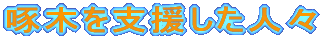
| 1.啄木と金田一京助 (4) | |||||||
まだ啄木は寝ているようなので、金田一氏は一人で他の下宿を探しに出た。森川町の新坂上に真新しい三階建ての高等下宿があった。入ってみると、三階なら空いているという話で、下宿代を聞くと
、間代が五円で、食費が七円だという。前の下宿より二円高いだけだった。啄木用に適当な部屋がないか聞くと、布団部屋に使っていた二畳半の部屋があるということでそれに決めて帰ったが、啄木はまだ寝ていた。
「石川さん引越しだ、引越しだというと、むっくり起き上がって、『僕も連れてってと、手を揉んで拝むまねをした。』私は『勿論です早く起きなさい、素敵な下宿だから』啄木を金田一氏の部屋へ連れて来て、がらんとした本棚を見せると、『あっと驚き、僕のためだなあ、と言ってペコリと頭を下げた』金田一は打ち消すように『いえそうじゃない、柄にもない文学かぶれを清算して、これから一直線にアイヌ語へ進むの、私はこれで清々した。』」 こうした啄木に対する思いやりというものは、金田一氏なればこそのことであて、誰にでも出来るということではない。金田一氏は啄木を連れて新しい下宿を見せた。狭いが窓外の風景も良く、啄木も気に入ったようだ。「それでは新しい第一歩の門出だ、祝杯を挙げよう。」ということで、一品料理屋に入って、ビールを傾けた、だが金田一氏の胸中は複雑だった。「本の愛着というものがあって、この時のビール程様々な味をもったビールを飲んだことがない。」と言っている。これは彼の本音であろう。啄木を同居させなかったらこうした多大の犠牲を払うことはなかった。 新居に移ってから金田一氏は帳場の主人に「連れの石川君という人は、天才を謳われた人ですが、不幸にも今失職しているのです。私が責任を持つから、きつく当たらないで気長に待ってください。」と、啄木のために事前に釘をさした。主人は『ようがす、いずれ大晦日には下さるんでしょう』」ここの主人は日清戦争に従軍して功績をあげ、金鵄勲章を授与された人で、立派な相手だったから話も早かった。 啄木は張り切って仕事に打ち込んだ。長編小説「鳥影」を書いたのもこの部屋だった。当時「新詩社」での知人栗原古城氏は「東京毎日新聞」の文芸欄の担当であったが、急に小説の書き手に差し支えが出来て、他の書き手を依頼することになったとき、栗原氏の頭に浮かんだのは啄木が金に困っているという事だった。「一つ書かせてみるか」と主筆に相談して了解をとった。この小説は明治四十一年十一月一日から十二月三十日まで連載された。 十一月三十日に新聞社に出向き、一か月分の原稿料三十円を受け取った。この金は下宿代に消えたが啄木としては満足であった。「借金というものは返せるものなんだなあ、借金を返すということは、良い気持ちのものだなあ」と金田一氏に語っているが、彼はこれまで借金しても返したことがなかったのだから、こうした感想も出たのであろう。 下宿によく来ていた貸本屋の山本太市郎という爺さんがいた。啄木はいい客だったがある日、彼はその爺さんに、「君は方々の家庭へ入るだろうが、何処かに良い娘さんはないかね、あったら世話してくれ給え。こっちは文学士で大学の講師だ。」爺さんは「丁度心あたりがありますよ。」そして見合いの話まで決められた。当時金田一氏とすれば家を持つには収入不足だと思っていたし、見合いしては断りにくい。といったこともあった。だがこの話を実家に伝えたら、父親が飛んできて、トントン拍子に結婚が決まった。両親としてはなかなかそうした気のない息子を心配していたのだろう。 金田一氏は啄木に対して多大の犠牲を払った。半面啄木は金田一に何のお返しもしていない。しかしこの配偶者を間接的ではあるが世話した件は、唯一のお返しになったのではないかと私は考える。 啄木は何時までも金田一氏の世話にすがっているわけにもゆかず、家族を呼び寄せることさえできない。小説もそう簡単に金にはならないことがわかり、定収入を確保する必要から、明治四十二年二月三日「東京朝日新聞社」の郷土出身の編集長佐藤北江氏へ、駄目でもともとと言った気持ちで履歴書を送ってみた。
面会する回答があったのは四日後であった。啄木は日記に、「約の如く『朝日新聞社』に佐藤氏を訪い、中背の、色の白い、肥った、ビール色の髯をはやした無骨な人であった。三分ばかり話し三十円で使って貰う約束、夕方ニコニコしながら帰る。こっちさえ決まれば生活の心配は大分なくなるのだ。」これで安心は出来たが、家族をすぐ呼ぼうとはまだ決めていなかった。 しかし母かつは、 啄木も小説が新聞に出るようになり、就職もできたことから、充分家族を扶養出来るものと考えたのであろう、一方的に上京するから準備するように伝えてきた。啄木は名作「ローマ字日記」を書いていたが、なんの準備もしていなかった。 あわてて彼は郁雨氏に連絡して転居に必要な経費十五円を送ってもらい、新井理髪店の二階二間を借りた。明治四十二年六月七日、郁雨氏は家族を伴なって函館を発ち、途中母を野辺地で夫一禎のもとに行かせ、家族と郁雨氏は盛岡で下車して節子の実家落合家に入った。そこで待機していたが、啄木から十五日に上京せよという連絡が来た。家族の到着を「ローマ字日記」は「十六日の朝、まだ陽の昇らぬうちに、余と金田一君と岩本と三人は上野駅のプラットホームにあった。汽車は一時間遅れて着いた。友、母、妻、子と、車で新しい家に着いた。」で「ローマ字日記」は終っている。 ここで啄木は金田一氏と別れることになるが、「蓋平館」を出るに当たり、まだ未払いの下宿料が残っていた。百十九円余を月十円の月賦にしてもらい、金田一氏が保証人を引き受けてくれた。それで下宿を出られたのだが、この負債はなかなか支払えなかったようで、土岐氏が「新潮社」から「啄木全集」を出版した際の多額の印税によって完済された。 そのうち金田一氏も結婚して家庭を持ったから、当然ながら両者の交遊も疎遠になっていった。そうした中で、もともと意地の悪い母と節子との仲は日増しに先鋭となり、節子の体況も不調であった。その頃、妹ふき子が郁雨氏に嫁ぐことがきまり、「妹の嫁入り仕度を手伝いたいので盛岡へ帰りたい。」と申し出たが、啄木は許さなかった。 十月二日の朝、節子は京子を連れて家出したのである。後には置手紙が残されていた。「私ゆえに親孝行の貴方をお母さんに背かすのは悲しい。私は私の愛を犠牲にして身を退くから、どうかお母さんへの孝養を全うして下さい。」とあった。節子は、これまで不満があっても、啄木に背くような行為はなかった。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||

