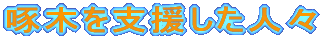
| 1.啄木と金田一京助 (2) | |||||||
| 食事も満足にできなかったから、心身ともに衰弱し、さすがの啄木も限界を感じたのであろう、親元に現状を報告して支援を求めた。父一禎和尚はただちに上京して連れ帰った。 啄木は故郷で通院して療養に努め、三ヶ月後には再び文学に対する意欲が芽生えたのだろう、「ワグネルの思想」という論文を書き「岩手日報」に七回連載したが以後中止した。 それには原因があった。明治三十六年十月、富山房はヨネ野口氏の詩集「東海より」を日本版として発行した。啄木はそれを新聞広告で知り、野口氏が米国の在住者であることが判明し、その点に注目した。当時啄木は渡米に強い希望を抱いていたから、野口氏に接近したいと考えたのであろう。
節子が自発的に歌集「東海より」を啄木に送ったように書いている研究者もあるようだが、私にはそうは思えない。野口氏は当時まだ国内では無名の詩人であったから、節子はその存在を知っていたとは考えにくい。啄木は医療費などに費用もかかることから、読みたいと思っても余裕の金がない、恋人節子に依頼して送ってもらったのだと考えるのが自然のように思う。 以後彼は詩作に没頭し、「東海より」の批評「詩談一則」を新聞に発表し、この論考もただちに野口氏に送った。また詩稿も後で送ると書き、長文の手紙を出している。その一端を示すと、「なつかしい大兄の高風に接すべく、如何にして己が渡航の機会―否費用を見付けたらいいのであろうか。」と述べ、ここには啄木の本音が見える。つまり野口氏からの援助を期待していたのである。しかし野口氏とて三十そこらの年であるから、そう楽な暮らしをしていたわけではない。いくら待っても野口氏からは何の返事も来なかった。 そんなことで、啄木の渡航熱も何時しか覚めていったのである。最初に作った詩五作は「明星」に発表したが、おおむね好評であった。これまで「白蘋」という雅号を使っていたが、この詩作から初めて「啄木」と署名し、以後生涯この雅号で通した。渡米も不調となった啄木は、以後詩作に専念した結果、詩作品も五十一篇にもなっていた。これだけあれば詩集の出版を考えるのは自然である。前年の上京は失敗したが、今度の上京にしても自信があったわけではない。 手持ちの金も少なく、事前に何も決まってはいなかったから、有力者の紹介で何とか出版にありつこうと考えていたのだろう、毎日詩人や歌人を訪問していたが、有力な援助は得られなかった。
こうなっては超大物の、郷土出身者である尾崎行雄東京市長を訪問するしかない。そのため原稿の献辞に尾崎行雄氏の名を加えた。尾崎氏は後に「啄木の嘲笑」という文章の中で、「一体勉強盛りの若い者が、そんなものにばかり熱中しているのはよろしくない。詩歌などは男子一生の仕事ではあるまい。」と叱ったというのである。啄木は叱られに行ったようなことだった。 ここで万策つきたわけではなかった。最後に思い出したのが、高等小学校時代の友、小田島真平氏であった。この件は章をあらためて詳述するのでここでは結果だけ述べておくことにしたい。次男小田島周三氏の支援で結局詩集「あこがれ」は出版されたのである。 さてその頃、渋民の両親には重大な事件が降りかかってきた。宗費を滞納したために住職の地位を奪われたのである。 石をもて追はるるごとく ふるさとを出でしかなしみ 消ゆるときなし 両親は寺を出て盛岡の一軒家に移った。これが啄木の「新婚の家」として現在も名所となり保存されている。金田一氏は啄木がどうしているのか心配になり、冬の休暇に訪ねてみた。「石川君は無精髪をそのまま長く伸ばして肩の上まで垂れ、芝居の由井正雪のような格好をしていた。正月は郷土の若い誌友を集めて歌会を開き、節子さんも交じって、さしずめ晶子夫人の役を演じて、夜は徹夜カルタ会を催すなど盛んなもので、これが半生の流転の前のほんのしばしの安息だった。」と延べている。 金田一氏のような堅実な生活者から見れば、啄木の生活態度などには驚いたことだろう。収入の全くないこの家庭の様子を見れば、当然遠からず破綻するのは目にみえている。金田一氏はあきれて去った事だろう。家賃を払えず、結局再び渋民へ帰るよりしかたがなかった。寺には入れないので、農家の二階に住むこととし、啄木もこうなっては就職して何がしかの賃金を得る必要にせまられた。 節子の父忠操氏は郡役場に勤めていたが、同僚に視学の平野喜平氏がいた。彼に何とか代用教員の口でも世話してくれるように頼んだ。平野氏は正規の教員を転勤させてまで啄木の席を用意したのである。こうして代用教員の職を得ても八円の月収では満足な生活は出来ない。したがって啄木は小説で収入を得ようとした。書くために学校を休むことも多くなり、「日本一の代用教員」を目指すなどと書いても普通の教員生活さえ満足に出来ないようでは、下等の教員でしかない。 だが次の事件ともなれば、教員の資格さえ捨てることになる。四月十九日、彼は高等科の生徒を引率して校門を出た。遠藤校長は校長として足りないところがある。という理由にもならない理由を生徒に押し付けてストライキを決行したのである。その結果校長は転勤させられ、啄木は当然免職になった。純真な子供らを自己都合で巻き込んでストライキなどするような教師が居るだろうか。教員の失格者といわれてもしかたがない。 彼はかねて函館の同人誌へ詩を送っていた関係で、同人松岡路堂氏に函館に行きたい希望のある事を相談してみた。松岡氏から折り返し歓迎するとの返事を受け取り、彼は函館ならば文学的土壌もあり、小樽にも近いので函館行きを即決した。ついては妻子を実家へ帰し、妹光子を小樽の姉夫婦に預けることにして、光子だけを伴って四月四日渋民を後にした。 翌日函館に到着し、光子だけはその日小樽へ発たせた。函館の友人達は啄木の為によく支援してくれ、弥生小学校の代用教員に世話してくれた。、月給は十二円で渋民よりは四円高かった。これで何とか家族を引き取れると考え、節子と京子が函館に着いたのは五月五日だった。しかしこの夫婦には不運がつきまとった。函館に来てやっと落ち着くことが出来ると思ったのもつかの間に過ぎず、この年八月二十五日の夜、明治時代最大の大火が市街の三分の二を焼き尽くしたのである。 啄木はここでの職場をすべて失ったので、札幌に行っていた同人向井氏に履歴書を託し就職を依頼した。家族は小樽の山本家に行く以外に道はなかった。向井氏からの連絡で札幌の「北門新報」に校正係りの口があるという。 |
|||||||
| もくじに戻る | |||||||

